なぜ『海がきこえる』は“ジブリっぽくない”と感じられるのか
『海がきこえる』を初めて観たとき、
「これ、本当にジブリ作品なの?」と感じた人は多いのではないでしょうか。
- 空を飛ぶわけでも
- 魔法が出てくるわけでも
- 壮大な自然や異世界が広がるわけでもない
それどころか、描かれるのは“とある地方都市の高校生たちのちょっとした青春の揺れ”。
静かで、地味で、淡々とした物語。
でも、なぜか心に残ってしまう──
“ジブリらしくなさ”が放つ魅力
『海がきこえる』は、間違いなくスタジオジブリ作品です。
でも、私たちが思い描く“ジブリらしさ”からは、大きく外れている。
それはなぜなのか?
そして、その“らしくなさ”がなぜ一部のファンに深く刺さるのか?
本記事では、『海がきこえる』を“ジブリらしくないジブリ作品”として位置づけ、
その特徴と魅力を読み解いていきます。
キーワードは、リアリズム・静けさ・等身大の青春。
あなたの中の“ジブリ観”が、少しだけ揺らぐかもしれません。
「ジブリ=ファンタジー」のイメージとのズレ

スタジオジブリと聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、
ファンタジーの世界や空を飛ぶ少女、喋る動物たち、不思議な生き物たちではないでしょうか。
- 『天空の城ラピュタ』の空中都市と冒険
- 『となりのトトロ』の森の精霊たち
- 『魔女の宅急便』の空飛ぶ配達
- 『千と千尋の神隠し』の異世界での成長
これらは、まさに“ジブリらしさ”の象徴ともいえる作品群です。
『海がきこえる』には“ファンタジー”が一切ない
それに対し、『海がきこえる』はどうか。
- 舞台は現実の高知と東京
- キャラクターはごく普通の高校生
- 起こる出来事も、友人関係やすれ違い、進路の悩みなど
- 非現実的な要素は一切なし
このように、ジブリにしては珍しい「完全なる現実世界の物語」なのです。
観る人が抱える“先入観”とのギャップ
この“ジブリ=ファンタジー”という先入観があることで、
『海がきこえる』はどうしても異質に見えてしまいます。
しかし、その異質さこそが、作品をユニークな立ち位置に押し上げている。
「ジブリがファンタジーを描かなかったら、何が残るのか?」
その問いに対するひとつの答えが、この作品なのです。
大人ではなく“等身大の10代”を描いた群像劇

『海がきこえる』の登場人物は、ほとんどが高校生。
しかも、特別に個性的なキャラが登場するわけではありません。
- 無気力気味の主人公・拓
- 自由奔放で読めないヒロイン・里伽子
- 真面目な親友・松野
- そのほかの同級生たちも、どこにでもいるような存在
この“普通さ”こそが、『海がきこえる』のリアリティを支えています。
成長を描くのではなく、“揺れ”を描く
ジブリ作品の多くは、主人公が何かを乗り越えて成長する物語です。
ところがこの作品では、
- 明確な成長は描かれない
- 問題が解決するわけでもない
- ただ、“あの頃の気まずさ”や“通じなかった気持ち”が残る
つまり、『海がきこえる』は“通過点”としての青春を描いているのです。
登場人物に“答え”を与えない構造
誰もが未完成で、言葉足らずで、すれ違ってばかり。
けれどその曖昧さが、まさにリアルな10代の群像劇。
観る人は、「自分もこうだった」と感じながら、
キャラクターたちの迷いや不器用さに共感するのです。
『海がきこえる』は、「ジブリ=子どもから大人への成長物語」という図式からも外れている。
それが、“ジブリらしくない”と言われる一因でもあり、
同時に、“刺さる人には深く刺さる”魅力でもあるのです。
派手な音楽・演出を抑えた“静の美学”

ジブリ作品といえば、久石譲の壮大な音楽や、
感情を高めるような印象的なシーンを思い浮かべる人も多いでしょう。
- 風を切るように飛ぶ空中シーン
- クライマックスで流れるメインテーマ
- キャラクターの感情が爆発する場面
しかし、『海がきこえる』にはそのようなドラマチックな演出はほとんど存在しません。
音楽は“空気”を作るためのもの
劇中に流れるBGMはとても控えめで、
感情を煽るのではなく、静かに“余白”をつくる存在です。
- 会話のあとに訪れる沈黙
- 放課後の教室に響く環境音
- 電車の揺れや風の音が印象に残る構成
こうした演出が、“間”のあるリアルな青春を際立たせています。
映像も“抑制された感情”を丁寧に映す
- 顔のアップではなく、あえて引いた構図
- 感情をぶつけず、すれ違ったままの人間関係
- 無言のカットがそのまま流れる時間感覚
これらはすべて、「語らないことで、観る人に考えさせる」という演出意図の表れです。
『海がきこえる』は、
何も起きていないようで、心の中では何かが確かに動いている──
そんな“静かなるドラマ”を描いた異色作です。
その抑制された美しさは、まさに“静のジブリ”とも言えるでしょう。
実は“ジブリらしくない”からこそ記憶に残る
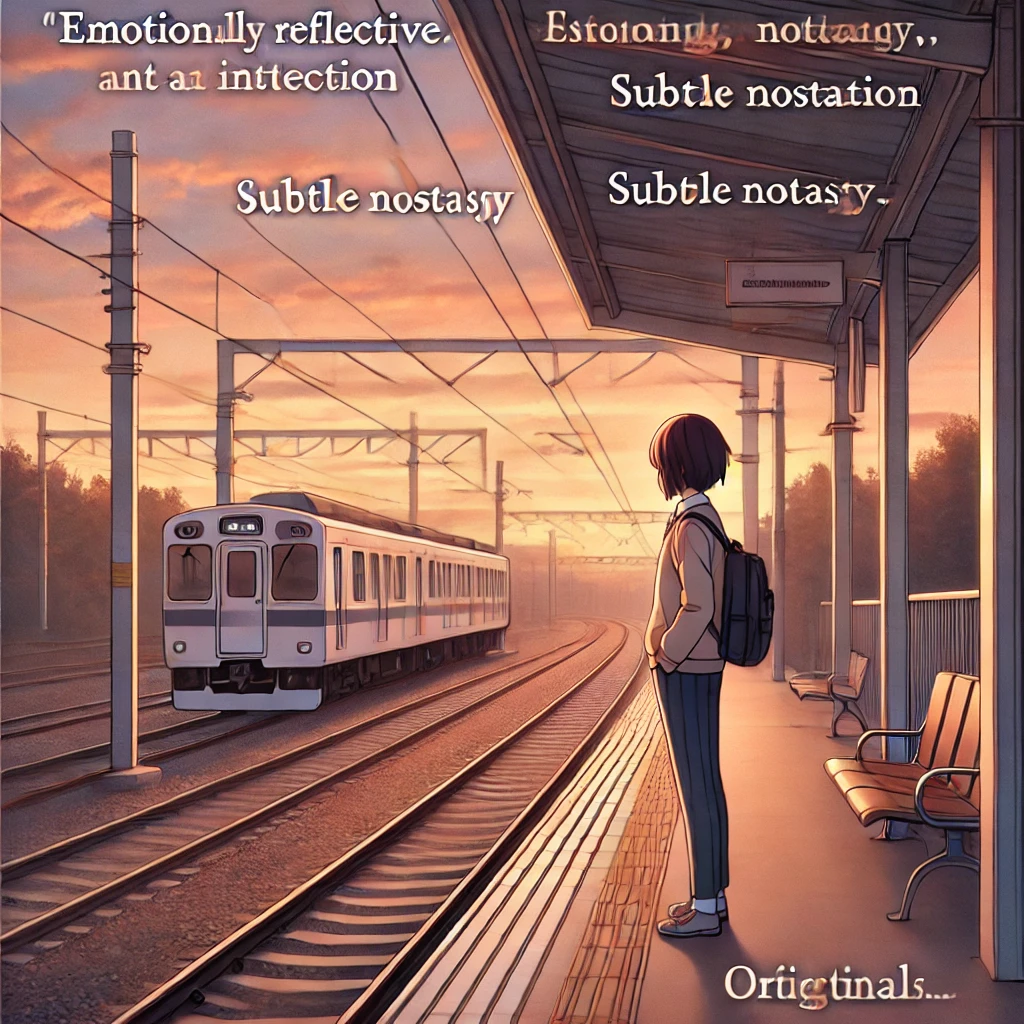
『海がきこえる』は、“ジブリらしさ”をあえて削ぎ落としたような作品です。
けれど、その“異質さ”こそが、観る者の記憶に深く刻まれる理由でもあるのです。
“観客に委ねる構造”が共感を呼ぶ
多くのジブリ作品は、
キャラクターの成長や結末がしっかりと描かれます。
しかし『海がきこえる』では、
- 誰も正解を持っていない
- 問題は解決しないまま
- でも、どこか「わかる」と感じてしまう
という、未完成な感情をあえてそのまま残す構造になっています。
それによって、観る側が自分の経験や感情を重ねてしまう。
つまり、「物語を観る」のではなく、「物語に参加する」という体験が生まれるのです。
“静かさ”があとから効いてくる
観終わった直後は「何も起きなかったな」と感じる人もいるかもしれません。
でも時間が経つほど、ふとしたときに思い出す──
- 窓辺の光景
- 言えなかった一言
- 電話越しの沈黙
そういった断片が、じわじわと記憶の底に残っていく。
この“静かな余韻”こそが、『海がきこえる』の真の魅力なのです。
“ジブリらしくなさ”は、決してマイナスではない。
むしろそこに、ジブリの懐の深さと可能性が垣間見えるのです。
結論:“らしくなさ”が生んだ、ジブリのもう一つの可能性
『海がきこえる』は、スタジオジブリ作品の中でも特に異色の存在です。
ファンタジーでもなければ、冒険譚でもない。
派手な演出もなければ、明確な成長や感動のクライマックスもない。
それでも、多くの人の心に残り続けるのはなぜか──
それは、“ジブリらしくない”という点こそが、この作品の核だからです。
“人間の心”を静かに見つめる物語
『海がきこえる』が描いたのは、
青春の中で言えなかったこと、気づかなかった想い、
そして時間を経てようやく振り返ることのできる記憶です。
それは、大げさに語られることのない、
誰の心にもひそむ“揺れ”や“余白”を丁寧にすくい上げた物語でした。
ジブリ=ファンタジーという固定観念を壊す
この作品を知ることで、私たちは気づきます。
スタジオジブリは、「空を飛ぶ」だけのアニメスタジオではない。
“人を描く”ことに徹底して向き合ってきたスタジオなのだと。
『海がきこえる』はその証明であり、
同時に、ジブリが描ける世界はまだまだ広がっているという可能性でもあります。
“ジブリらしくないジブリ作品”──
だからこそ、私たちの記憶にいつまでも残り続けるのです。



コメント