1. 導入|なぜあの瞬間、シータは名乗ったのか?
「私は、ラピュタ王家の末裔…」
──あのシーンを覚えているだろうか。
序盤では自らの出自をひた隠しにしていたシータが、
物語終盤、ムスカの前で突然“王族”を名乗った瞬間だ。
この言葉は、ただの血筋の確認ではない。
シータが“逃げる側”から“向き合う者”へと変わった象徴であり、
「継承の物語」における最も重要な転機だった。
2. シータに流れるラピュタの“血”の意味とは?

飛行石が彼女に反応する。
それは、ラピュタ王家の血を引く者であることの“証”だ。
だが、物語の構造は単純な「王族の復活」を描いてはいない。
- シータが王家の末裔であることは、彼女自身も“後から気づいた”
- 王家としての特権や権威を行使することもなかった
- それどころか、その血筋が“世界を壊す力”を持っていると知ってからは、それを恐れ続けていた
つまり、“血”は力ではなく、
「過去から受け継いでしまった責任」として描かれている。
3. “名乗らなかった”前半のシータは何を恐れていたのか?
祖母から“飛行石”を託され、
「誰にも見せず、名乗らず、生き延びなさい」と教えられた少女。
- 飛行石の力=人を傷つける力
- ラピュタの存在=人の欲望を呼び寄せる鍵
- 王家の血=戦争を引き起こす因子
だからこそ、彼女はずっと“名乗ること”を避けていた。
シータにとって、「王家の末裔」は誇りではなく、“呪い”に近いものだったのだ。
4. 「王族になる」とは「責任を背負うこと」だった

ムスカに対して「私は王家の末裔」と名乗ること。
それはただ血を証明する行為ではない。
- ラピュタを“止める権利”を主張するため
- 自分の出自と真正面から向き合うため
- 自らの手で「終わらせる覚悟」を示すため
その言葉には、
「私は逃げない」という強い意志が宿っていた。
つまり、シータは“王族として覚醒”したのではない。
“王族になる”という選択をしたのだ。
5. 「バルス」と共にシータが放った“意思の継承”

バルス──
ラピュタの崩壊を引き起こす、たった一言の滅びの呪文。
だがその言葉には、「破壊」以上の意味がある。
- 巨大な力を持つ王国=ラピュタを「終わらせる」選択
- 自らが持つ“血と権限”を、あえて“手放す”決断
- その上で“地上で生きていく”ことを選ぶ姿勢
バルスは、“支配の血を捨てる”ための言葉だった。
それは祖先の過ちを引き受けて、
未来へ“別の選択肢”を示す行為にほかならない。
6. まとめ|「血に目覚めた」のではなく「覚悟を継いだ」少女の物語
シータの旅は、「王族であること」を思い出す旅ではなかった。
それはむしろ、
“血に縛られる者”から、“意志で選ぶ者”へと変化していく旅だった。
- 生まれが自分を定義するわけではない
- だが、その生まれによって背負った責任からは逃げない
- そして最後には、自らの言葉で「終わらせる」力を行使する
それこそが、“王族になる”ということ。
そしてそれは、血ではなく「覚悟」によって継がれた王権だった。
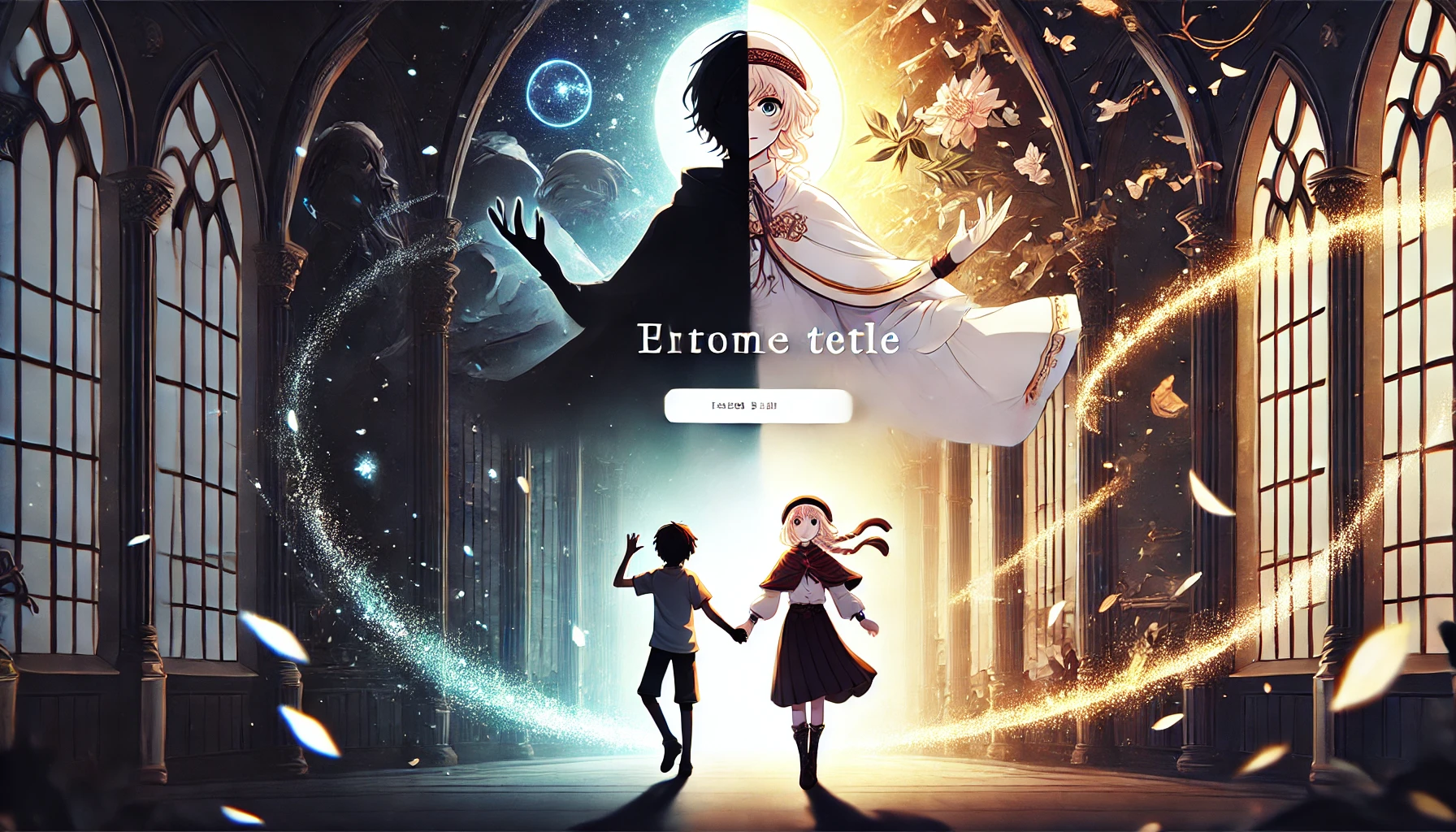


コメント